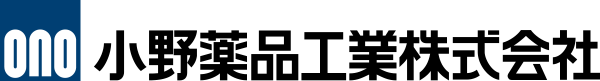臨床試験(治験)の実施について
臨床試験における法令等遵守と参加者の人権配慮
当社は、臨床試験を実施するにあたり、医薬品の臨床試験の実施に関する基準(GCP)など、各国の薬事規制、ヘルシンキ宣言ならびに医薬品規制調和国際会議(ICH)の各種ガイドラインを遵守します。臨床試験参加者の人権を最大限に尊重し、臨床試験参加者の安全性に細心の注意を払い臨床試験を実施します。また、治験参加者の個人情報の保護に努め、高い倫理感をもって臨床試験を実施します。なお、臨床試験の計画については、まず、社内の治験審査委員会において、倫理的な観点および科学的な観点から実施の可否を検討します。社内における検討の結果、実施可と判断された臨床試験については、最終的に治験実施医療機関の治験審査委員会での審査および承認というプロセスを経て、はじめて実際に実施されることになります。
参加者へのインフォームドコンセント
臨床試験への参加者には、試験の目的、方法、予測される利益と不利益、参加した後いつでも参加の取りやめができること、参加しなくても不利益を被らないことなどについて、治験担当医師から事前に十分な説明を行い、参加者の自由意思に基づく同意を取得します(インフォームドコンセント)。また、参加試験に関連する新たな情報が得られた場合には、参加者に速やかにその内容を説明し、治験継続の意思を確認します。
臨床試験の計画と実施
臨床試験の計画は、医学、薬学、統計学など、専門的な観点で十分な検討を経て立案されます。臨床試験は治験実施計画書に基づいて実施され、副作用情報の収集やリスク評価を行い、臨床試験参加者の安全性に十分配慮して実施されます。また、臨床試験が治験実施計画書やGCPに則って適切に実施されていることを定期的にモニタリングし、その結果、逸脱が認められた場合には、原因究明や再発防止策を講じて、臨床試験が常に適切に実施されている状態を確保します。
教育研修とモニタリング
GCPやICHの各種ガイドラインを遵守して臨床試験が行われるよう、臨床試験に関わる社員や実施医療機関に対して必要なトレーニングを実施しています。また、治験実施計画書や各種手順書に関するトレーニングも行い、予め設定した試験計画や手順に則り臨床試験が実施される体制を整えています。臨床試験の実施に関わる業務を開発業務受託機関(CRO)に委託する場合においても、CRO担当者がGCPや各種規制を遵守して業務を行なえるよう、必要な教育研修が行われていることを確認し、委託した臨床試験業務が適切に実施されているかを定期的に監査します。
臨床試験データの管理と開示
当社は、臨床試験データおよびその結果を研究者や医療従事者、患者さんなどと共有することは、科学研究や医学研究の促進に貢献し、公共の利益につながると考えており、「臨床試験データの公開に関するグローバルポリシー」を定め、外部のウェブサイトを通じて公開しています。なお、臨床試験に参加された患者さんの個人情報に関しては、法令や自社で定める社内規程に従い、適法かつ適正な手段によって管理し、同意を得ている利用目的の範囲内で取り扱うとともに、公開に関しては匿名化などを行い、患者さんの個人情報を保護します。
詳細については「臨床試験データの公開に関するグローバルポリシー」をご確認ください。
臨床試験終了後の治験薬へのアクセス
臨床試験の対象疾患が重篤な疾患かつ他に代替可能な治療法がない場合においては、治験実施計画書に定める有効性および安全性の評価がすべて完了し、当該臨床試験が終了した後であっても、参加された患者さんの医学的状態等に応じて、治験治療を継続することを可能とする試験計画への変更を行うなど、倫理的な配慮をもって試験計画を立案しています。例えば、国から製造販売の承認を得た後、医療機関での処方が実際に可能となるまでには一定の期間が必要となる場合がありますが、そのような場合に治験に参加いただいた患者さんが引き続き治験薬による治療が受けられるよう、治験を製造販売後臨床試験に切り替えて継続する場合などが該当します。また、当該開発品が開発の最終段階にある場合には、医療機関からの要望に応じ、臨床試験に参加できなかった患者さんに対して、治験薬投与を可能とする臨床試験(拡大治験)の実施を検討しております。
ヒト由来試料を用いた研究における倫理的配慮
医薬品の研究開発において、ヒトにおける有効性や安全性を予測するための有効な手段として、ヒト由来試料(血液、組織、細胞、遺伝子など)を用いた研究を行います。そのような研究の実施に際しては、当該研究の必要性、有用性について試料提供者の理解と同意を得るとともに、研究の過程で知り得た個人情報を適切に管理してプライバシー保護に努めるなど、倫理的な配慮が不可欠です。特に遺伝子解析を伴う研究については、試料提供者ばかりでなく血縁者の遺伝的素因を明らかにすることにもつながり、その取り扱いによっては、様々な倫理的、法的または社会的問題を招く可能性があることを十分に認識しておく必要があります。また、ヒト胚性幹細胞(ES細胞)の研究利用は、ヒトES細胞が人の生命の萌芽であるヒトの胚を壊して作製されたものであること、あらゆる細胞に分化する能力をもつことから、生命倫理上の懸念点を有することを認識しています。ヒトES細胞の研究利用にあたっては、関係法令および指針を踏まえ、社内の倫理委員会において慎重に検討すべきと考えております。
当社では、ヒト由来試料を用いた研究を適正に実施するために、国の基本指針(「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」)に基づいた社内規程を定めています。また、諮問委員会として「人を対象とする医学系研究」倫理委員会を設置し、各研究計画の倫理的および科学的妥当性を厳正に審議しています。本委員会は、学識的かつ多元的な視点から公正かつ中立的な審査が行えるように、倫理・法律を含む人文・社会科学面の有識者、自然科学面の有識者および一般の立場の者を含む社外および社内の委員で構成されています。
厚生労働省の倫理審査委員会報告システムを通じて、委員会規則や委員会名簿および議事の概要などを公表しています。
新興技術の利用における倫理的配慮
ヒト人工多機能性幹細胞(ヒトiPS細胞)および遺伝子治療のためのヒトゲノム編集などの新興技術は、疾患の原因究明や根本治療に応用できる可能性があり、当社もこれらの新興技術に注目しています。日本では「ヒトiPS細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針」において一定の要件に適合する限りヒト生殖細胞を作成する基礎研究は容認されている一方で、人工的に作られた生殖細胞を用いてヒト胚を作成することは禁止されています。当社も当該指針に従って、人工的な生殖細胞からヒト胚を作成する研究は実施いたしません。
新興技術を利用する場合、関連する法律や指針を遵守し、倫理面に配慮しながら、これらの技術を慎重に取り扱います。
動物実験における倫理的配慮
当社は、人々の健康な生活に役立つ医薬品を開発して社会に貢献したいと願っており、そのためには実験動物を用いた創薬研究が必要不可欠です。こうした実験動物を用いた研究は、動物福祉の観点から動物の生命を尊重し、動物に出来る限り苦痛を与えず、必要最小限の動物数で目的が達成されるものでなければならないと考えています。
このため、当社では「動物の愛護及び管理に関する法律」およびそれに関連する指針に則り、動物実験に関する社内規程を定めています。動物実験を実施するまでには、コンピューターシミュレーションやin vitroの評価系において標的分子や化合物の評価を行い、動物実験で評価する化合物を絞り込むことで3Rs*1に取り組んでいます。動物実験は動物実験委員会で3Rsの観点から審査され、承認された実験計画のみを実施しています。また、動物実験に関する法律や指針、社内規程、実験動物の取り扱い等の教育研修を受講した者だけが動物実験に携わっています。
さらに、当社で動物実験を実施している施設毎に、法律・指針・社内規程への適合性について年1回以上自己点検・評価を実施するとともに、一般財団法人日本医薬情報センター動物実験実施施設認証センター*2による認証を取得し、継続的に更新しています。また、毎年、動物慰霊祭を執り行い、動物に感謝の意を表するとともに、その霊の安らかなることを祈念する場としています。
*1 3Rs
Replacement: 動物を用いない代替試験法を活用すること
Reduction: 使用する動物数を必要最小限にすること
Refinement: 動物に無用の苦痛を与えないようにすること
*2 厚生労働省の所管する動物実験実施機関における動物実験等の実施に関して、動物実験等の自主管理の促進とともに動物愛護の観点に配慮しつつ、科学的観点に基づく適正な動物実験等が実施されているかを外部評価・検証する事業を行う一般財団法人日本医薬情報センター内に設置された組織
遺伝子組換え生物
当社は新薬の研究開発、抗体やタンパク質の産生、細胞治療研究のために遺伝子組換え生物を使用しています。「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)」に基づいて定めた社内規程を遵守することによって、遺伝子組換え生物の環境中への拡散や漏洩を未然に防止しています。また、これらの研究試料の適切な利用を推進するため、社内委員会において実験従事者の教育訓練や実験申請の審査を継続して実施しています。
臨床研究 オプトアウト
当社は、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(以下「倫理指針」)および「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、研究を行っています。
既存試料・データの研究目的での使用に際しては、研究の対象者となる方から事前に同意を取得することを原則としています。しかしながら、提供を受けた臨床研究の終了により連絡先情報が確認できない等の理由で同意をいただくことができない既存試料・データを用いる研究については、倫理指針に基づき、研究内容を公開し、研究の対象者となる方から拒否できる機会を設けております。このような方法を『オプトアウト』といいます。
ご自身の既存資料・データが使用されることを希望されない場合は、オプトアウト欄を参照し、お問い合わせ先にご連絡ください。
オプトアウトを実施している臨床研究は下記の通りです。